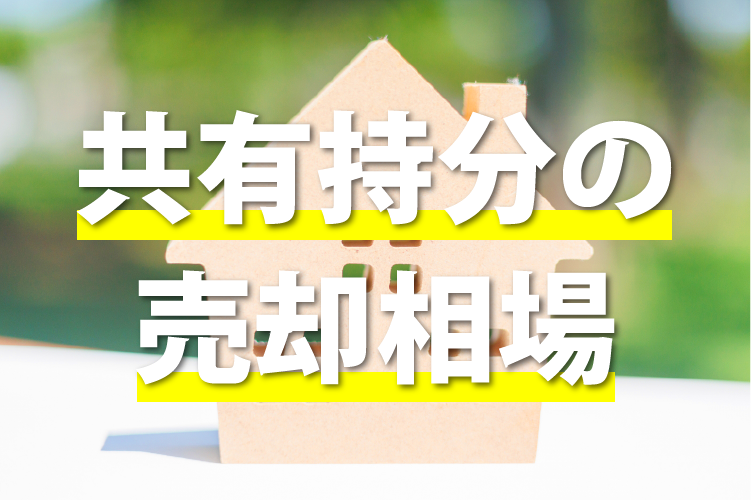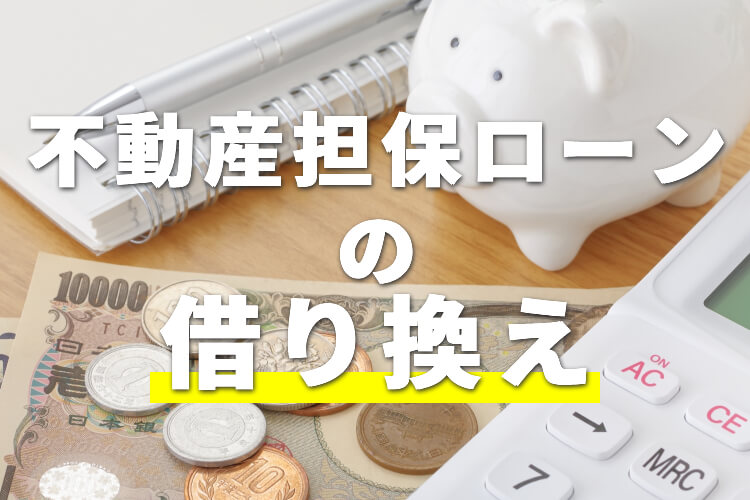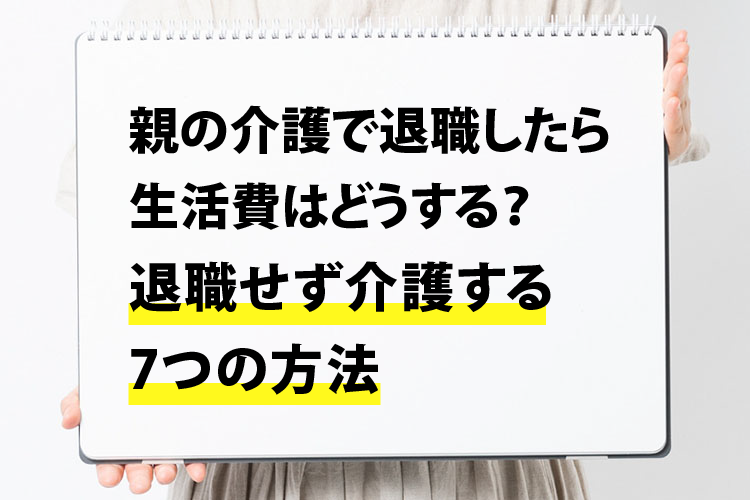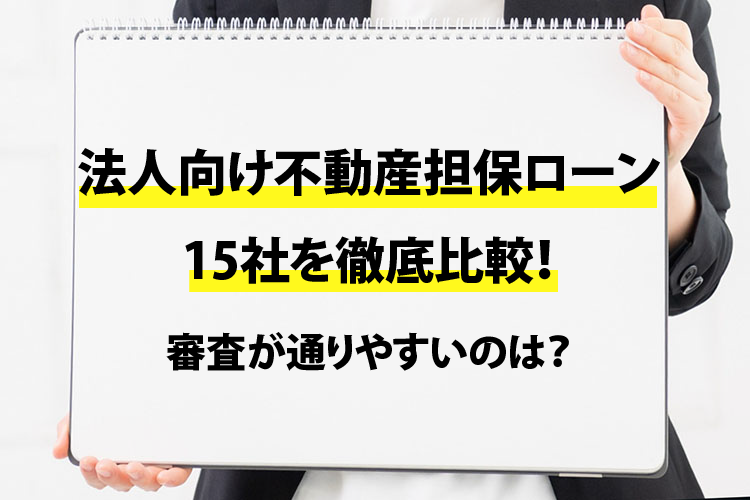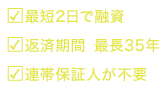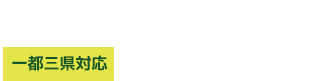「共有不動産ってトラブルが多いの?」
「共有不動産のトラブルって、どんなトラブルが多いの?」
と悩んでいませんか?
不動産の取り扱いには、大きなお金が関わりますので、いざトラブルが起こると一大事になってしまいます。
できれば避けたいですよね。
このページでは、共有不動産の6つのトラブル例やその解決方法について、共有不動産のプロが解説していきます。
目次
共有不動産とは?メリットも解説
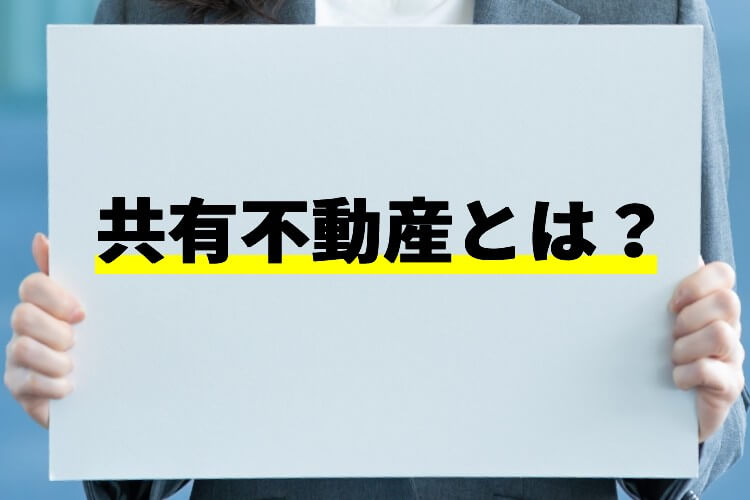
共有不動産とは何か、どんなメリットがあるのかをご案内していきます。
知っておこう!共有不動産とは…
複数の人が一つの不動産(土地や建物)を共有している状態のことです。
複数の人が共有してる状態を共有名義といいます。
不動産が共有名義になるパターンは、主に次の2つです。
- 相続や贈与で親や兄弟・姉妹で共有する
- 夫婦でマンションを購入する
共有者は不動産全体に対する所有権(共有権)を持っています。
共有物全体に対する所有権の比率を「持分」と呼びます。
共有比率に関わらず、不動産の使用や利益などを共有できますが、持分によって権利や義務の大小が決まります。
例えば、AさんとBさんが共有名義で不動産を所有していて、Aさんの持分が2/3、Bさんの持分が1/3であれば、Aさんはより大きな権限を持っているということです。
共有不動産の5つのメリット
共有不動産のメリットは5つあります。それぞれ詳しくしていきます。
①購入負担が軽減される
共有名義で不動産を購入するということは、複数の人で購入するということです。
そのため、一人で全額を負担するより購入しやすくなります。
例えば夫婦で5,000万円のマンションを購入する場合、夫が2,500万円、妻が2,500万円支払いをするといったことです。
②維持管理費、固定資産税の分担ができる
不動産を維持するには、税金や修繕費といった維持管理費が必要です。
一般的に、共有持分に応じて分担します。
例えば、年間の維持費が30万円で、あなたの持分が1/3なら、10万円の負担をするということです。
③住宅ローン控除が適用がされる
共有名義人全員が住宅ローンの借り手となり、全員がローンを返済する場合、各借り手が個々に住宅ローン控除を受けられます。
例えば夫婦でマンションを購入し、持分の割合が50:50なら、次の計算式で算出できます。
住宅ローン残債(残高)×持分×1%
3,000万円x50%x1%=15万円
④相続対策になる
相続前に、一定の持ち分を子供などに移すことで、相続税の節税ができます。
相続が発生した場合、親の持分にだけ相続税がかかるからです。
税金の具体的な内容については、税理士とやり取りをしてください。
⑤特別控除が受けられる
共有名義の不動産を売却して得た譲渡所得に、特別控除が適用されます。
所得税法に基づく税制優遇措置です。
具体的には、次の条件を満たした場合に税額が軽減されます。
- 居住用財産を売却する
- 売却後に新たな居住用財産を購入する
- 一定の期間内に売却が行われる
譲渡所得は、売却価格から取得費や改修費を差し引いて算出されます。
共有不動産で起きやすい6つのトラブルを解説
- 利用方法について意見が対立する
- 費用負担について意見が対立する
- 不動産の価値が下落する可能性がある
- 共有者が増加する
- 年々リスクが拡大する
- 共有者が見つからず不動産活用ができない
6つのトラブルについて詳しくご案内していきます。
【トラブル①】利用方法について意見が対立する
不動産の活用方法は賃貸にしたり、リフォームして住み続けたりと、色々あります。
意見が対立するとは、例えば、父と子で共有している建物があり、父が「年金代わりに賃貸にしたい」と考えているのに、子は「改築して夫婦で住みたい」と考えているようなケースです。
お互いの経済状況がありますので、このようなケースでは話せば話すほど溝は深まってしまいます。
共有者間で事前に利用方法についての話し合いをし、合意を取っておくことで防ぐことができます。
ただ、状況は常に変わりますので、「こんなはずではなかった…」という結果になることもあります。
【トラブル②】費用負担について意見が対立する
先ほどもご案内したように、不動産の活用方法にはいろいろあります。
例えば、家をリフォームする場合、使用頻度や所有比率に応じて費用負担するのが一般的です。
事前に明確な合意を形成しておくことでトラブルを防ぐことができます。
ですが、経済状況によっては、費用の負担の割合や額について、共有者間で見解が合わないことがあります。
【トラブル③】不動産の価値が下落する可能性がある
次のような費用については、共有者全員で適切に管理する責任があります。
- 建物の維持や修繕、税金の支払い
- 賃貸アパートの運営にかかる費用
- テナントの入っているビルの費用
共有名義人が増えれば増えるほど管理責任が不明確になります。
責任の所在があいまいになり、不動産の維持管理が適切に行われなくなった結果、不動産の価値が下落してしまうことがあります。
弁護士に依頼して、事前に話し合いをしておくことで防ぐことができます。
【トラブル④】年々リスクが拡大する
不動産の共有名義人が死亡したら、その所有権は遺産として相続人に移転します。
新たな共有者が増えると権利関係が複雑化し、①~③でご案内したトラブルが発生するリスクが高くなります。
いつどのようなトラブルが発生するか分からず、発覚した時には修復不能な一大事になっていることが多いです。
【トラブル⑤】共有者が見つからず不動産活用ができない
不動産の共有者が増えた結果、共有者がどこにいるのか見つけられなくなることがあります。
- どこに住んでいるのか分からない
- どこに連絡すればいいのか分からない
- ご存命なのか分からない
共有者の承諾が得られないため、不動産を活用することができません。
この場合、まずは戸籍謄本や住民票などを利用して探します。
それでも見つからない場合は、次のようなの法的手続きを実施すると、活用できるようになります。
- 共有物分割訴訟
- 遺産分割調停
手続きには相応の費用と時間がかかります。
【トラブル⑥】 売却時に共有者間の意見が一致しない
共有物全体を売却する際、全ての共有者が売却に同意しなければ進められません。
ですが、共有者全員が売却に同意しないケースはとても多いです。
売却するにしても「もっと高く売れるのでは?」「私の取り分を増やしてほしい」といったことで進まないことがあります。
この他に、それまでの関係から(あいつの利益になるなら賛成しない)という方もいます。
共有不動産のトラブルで困ったときはどうしたらいい?
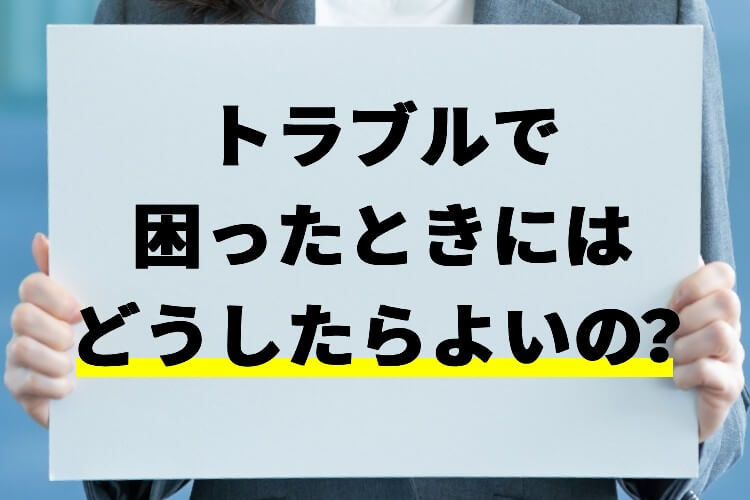
次のような方法があります。
- 共有者間での話し合い、すり合わせ
- 専門家(弁護士、税理士)による意見調整
- 法的手段(共有物分割訴訟、遺産分割調停)を取る
- 自分の持分だけで売却、借入をする
トラブルを起こさないようにするためには、共有者全員で事前に納得するまで話し合っておくことが重要です。
大きい不動産の場合は、意見が対立しないように、弁護士や税理士に入ってもらって、意見調整をすることがあります。
それでも状況によっては、一度決めた意見が変わることがあります。
各共有者の経済状況や人間関係による感情のもつれがありますので、一度トラブルが発生すると解決するのが難しいです。
場合によっては、共有物分割訴訟や遺産分割調停をすることがあります。
共有物分割訴訟とは、不動産所有者のうちの一人が、残りの不動産所有者に対して、「不動産を自分一人の名義にさせて欲しい」と申し出る行為のひとつです。
詳しくはこちらの「共有物分割請求とは?メリット・デメリットを解説」でご確認いただけます。
この他の解決案としては、あなたの持分のみを売却したり、持分を担保に不動産担保ローンを利用したりする方法があります。
共有不動産の売却は勝手にできない?
- 全持分を一度に売却する
- 自分の持分だけを売却する
- 他の共有者に持分を売却する
共有不動産のうち、あなたの持分だけなら売却や借入に利用できます。
自分の持ち分を売却した場合には、新たな持ち主が共有者となり、既存の共有者と同じ権利を享受することになります。
これらの詳細は民法第251条〜第256条で規定されています。
- ・民法の表
| 該当する民法 | ポイント |
|---|---|
| 第251条:共有物の処分の要件 | 共有物を処分し、又は共有物について第四編の規定による契約をするには、共有の全員の同意が必要である。 |
| 第252条:共有者の持分売却の禁止 | 共有物に係る権利を有する者は、その持分を第三者に譲渡することができない。 |
| 第253条:共有物の処分についての協議の義務 | 共有者は、共有物の処分について、相当の注意を払い、誠実に協議しなければならない。 |
| 第254条:共有者の一方が独断で処分を行った場合の取り消し請求権 | 共有者の一方が、相当な事由なく独断で処分をしたときは、他の共有者は、その処分を取り消すことを請求することができる。 |
| 第255条:共有者の一方が独占して処分を行った場合の損害賠償請求権 | 共有者の一方が、共有の物を独占して処分し、その結果損害を受けた場合、他の共有者は、その損害を賠償することを請求することができる。 |
| 第256条:者の一方が処分したものが第三者に移転した場合の権利行使 | 共有者の一方が、その処分により共有物が第三者に移転したときは、他の共有者は、その共有物の取得を第三者に対して主張することができる。 |
より詳しくは、こちら法令検索でご確認ください。
共有不動産の持分を売却するとどうなる?相場や税金について
共有不動産を売却する手順をご案内します。
【ステップ①】持分の割合を確認する
登記事項証明書で、自分の持分を確認します。
あなたの持分だけなら売却できます。
【ステップ②】売却依頼先、価格の決定をする
売買の依頼先は、共有不動産を専門に扱う不動産会社がおすすめです。
複数の会社にあなたの持分の査定依頼をして、比較した上で決定してください。
売却の相場は次の要素で変わりますので、一概には算出しづらいです。
- 場所
- 規模
- 状態
- 持分の割合
例えば、全体の評価額が6,000万円の不動産のうち、あなたの1/6の持分でも1,000万円とはなりません。
会社によりますが、6割ぐらいの600万円ぐらいだと捉えておいてください。
【ステップ③】売買契約の締結をする
不動産会社を通じて、買い手が決まったら契約を締結します。
契約書には、次のことが記載されています。
- 売買の対象となる共有持分
- 売買価格
- 支払い方法
- 引渡し時期
【ステップ④】登記手続きをする
売買を公的に証明するために、法務局で新しい所有者の名義に変更する「登記」を行います。
この手続きで所有権が購入者に移転します。
【ステップ⑤】売買代金を受け取る
売買代金を受け取ります。
売却した後に発生する税金は次の通りです。
- 所得税
- 住民税
具体的な税額は売却益額で変わります。
【ステップ⑥】引渡しをする
共有持分の引渡しを行います。
このとき、引渡し証明書を作成し、双方で確認・署名・捺印をする必要があります。
丸の内AMSでは、共有持分の不動産に知見のある弁護士と提携をしていますので、お力になれると思います。お気軽にお問い合わせください。
共有不動産のトラブルに関するまとめ
共有不動産では、利用方法や費用負担での対立、不動産価値の下落などトラブルが起こる場合があります。
これらを防ぐには、事前の話し合いや専門家のサポートが重要です。
万が一トラブルが発生した場合や解決方法について知りたい場合は、丸の内AMSにご相談ください。
専門家と提携し、適切なサポートを提供いたします。
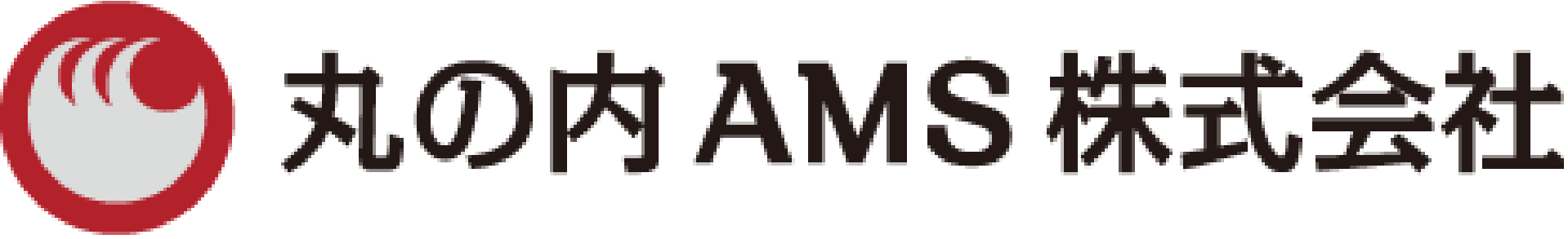
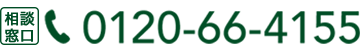

 不動産担保ローン
不動産担保ローン